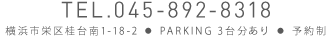キシリトールの特徴
キシリトールの特徴
歯の健康によい甘味料として、キシリトールは国民に広く浸透しています。キシリトールには、う
蝕予防に適した次のような①~⑤の生化学的特徴があります。
①野菜や果物など、自然界に分布する天然の5炭糖の糖アルコールであり、相対甘味度1、すなわち
砂糖と同等の甘味を持っています。
②口腔細菌によって代謝されず、有機酸が産生されることはまったくありません。
一方で糖アルコールは、腸内細菌も代謝できず、腸管の吸収も悪いために、概ね体重1㎏あたり1g
程度の摂取でお腹がゆるくなる場合があります。
溶解するとき吸熱反応を起こすので、清涼感を伴います。キシリトールは、砂糖に匹敵する甘味
で、唾液の分泌を刺激し、それによって口腔内のカルシウムや重炭酸塩が増大する結果、歯の脱灰
防止と再石灰化促進作用が生じて、むし歯の発生を防止すると考えられています。
③キシリトールは、インシュリン非依存的に代謝されるので、血糖値に影響しません。糖尿病患者
も安心して摂取できます。しかしカロリーはスクロース75%(3kcal/g)と、ダイエット甘味料とは
とてもいえません。
④キシリトールは、ミュータンス連鎖球菌の糖質代謝を阻害する、いわゆる無益回路を回します。
ミュータンス菌は、キシリトールを取り込むとリン酸化して、キシリトール5リン酸(x-5’P)にしま
す。しかしミュータンス菌は、それ以降の代謝系を持たないので、菌体内に(X-5’P)が蓄積して糖代
謝系酸素を阻害するのです。
⑤FAO/WHO(共同食品規格委員会)より、『1日の許容摂取量(ADI)を特定しない』という最も高い安
全性を与えられています。
味覚習慣からみたキシリトール
このようにキシリトールは、う蝕予防にとって好都合な素晴らしい甘味料といえます。しかし味覚
形成においては、その推奨法、予防に使用する場面を注意深く検討する余地がありそうです。砂糖
と同等の相対甘味度1の味覚をあえて乳歯列完成前の幼児に積極的に摂取させるのは、いかがなもの
でしょう。歯を傷めてしまう人とまったく同じ味覚習慣をつけてしまう恐れがあります。
たとえば、乳幼児のう蝕予防では、ミュータンス連鎖球菌が感染する19ヶ月から31ヶ月の間のいわ
ゆる“感染の窓”の時期に、乳幼児本人ではなく、母親など菌を伝播しやすい人を対象にキシリトー
ルを用いるとよいかもしれません。う蝕予防のためには、スクロースは食事時に摂取し、食間にキ
シリトールなど機能性食品を摂取するといった、メリハリのついた食習慣が重要です。
キシリトールの本質は酸を作らないこと、唾液の分泌を促すことで脱灰予防にはたらくことです。


 キシリトールの特徴
歯の健康によい甘味料として、キシリトールは国民に広く浸透しています。キシリトールには、う
蝕予防に適した次のような①~⑤の生化学的特徴があります。
①野菜や果物など、自然界に分布する天然の5炭糖の糖アルコールであり、相対甘味度1、すなわち
砂糖と同等の甘味を持っています。
②口腔細菌によって代謝されず、有機酸が産生されることはまったくありません。
一方で糖アルコールは、腸内細菌も代謝できず、腸管の吸収も悪いために、概ね体重1㎏あたり1g
程度の摂取でお腹がゆるくなる場合があります。
溶解するとき吸熱反応を起こすので、清涼感を伴います。キシリトールは、砂糖に匹敵する甘味
で、唾液の分泌を刺激し、それによって口腔内のカルシウムや重炭酸塩が増大する結果、歯の脱灰
防止と再石灰化促進作用が生じて、むし歯の発生を防止すると考えられています。
③キシリトールは、インシュリン非依存的に代謝されるので、血糖値に影響しません。糖尿病患者
も安心して摂取できます。しかしカロリーはスクロース75%(3kcal/g)と、ダイエット甘味料とは
とてもいえません。
④キシリトールは、ミュータンス連鎖球菌の糖質代謝を阻害する、いわゆる無益回路を回します。
ミュータンス菌は、キシリトールを取り込むとリン酸化して、キシリトール5リン酸(x-5’P)にしま
す。しかしミュータンス菌は、それ以降の代謝系を持たないので、菌体内に(X-5’P)が蓄積して糖代
謝系酸素を阻害するのです。
⑤FAO/WHO(共同食品規格委員会)より、『1日の許容摂取量(ADI)を特定しない』という最も高い安
全性を与えられています。
味覚習慣からみたキシリトール
このようにキシリトールは、う蝕予防にとって好都合な素晴らしい甘味料といえます。しかし味覚
形成においては、その推奨法、予防に使用する場面を注意深く検討する余地がありそうです。砂糖
と同等の相対甘味度1の味覚をあえて乳歯列完成前の幼児に積極的に摂取させるのは、いかがなもの
でしょう。歯を傷めてしまう人とまったく同じ味覚習慣をつけてしまう恐れがあります。
たとえば、乳幼児のう蝕予防では、ミュータンス連鎖球菌が感染する19ヶ月から31ヶ月の間のいわ
ゆる“感染の窓”の時期に、乳幼児本人ではなく、母親など菌を伝播しやすい人を対象にキシリトー
ルを用いるとよいかもしれません。う蝕予防のためには、スクロースは食事時に摂取し、食間にキ
シリトールなど機能性食品を摂取するといった、メリハリのついた食習慣が重要です。
キシリトールの本質は酸を作らないこと、唾液の分泌を促すことで脱灰予防にはたらくことです。
キシリトールの特徴
歯の健康によい甘味料として、キシリトールは国民に広く浸透しています。キシリトールには、う
蝕予防に適した次のような①~⑤の生化学的特徴があります。
①野菜や果物など、自然界に分布する天然の5炭糖の糖アルコールであり、相対甘味度1、すなわち
砂糖と同等の甘味を持っています。
②口腔細菌によって代謝されず、有機酸が産生されることはまったくありません。
一方で糖アルコールは、腸内細菌も代謝できず、腸管の吸収も悪いために、概ね体重1㎏あたり1g
程度の摂取でお腹がゆるくなる場合があります。
溶解するとき吸熱反応を起こすので、清涼感を伴います。キシリトールは、砂糖に匹敵する甘味
で、唾液の分泌を刺激し、それによって口腔内のカルシウムや重炭酸塩が増大する結果、歯の脱灰
防止と再石灰化促進作用が生じて、むし歯の発生を防止すると考えられています。
③キシリトールは、インシュリン非依存的に代謝されるので、血糖値に影響しません。糖尿病患者
も安心して摂取できます。しかしカロリーはスクロース75%(3kcal/g)と、ダイエット甘味料とは
とてもいえません。
④キシリトールは、ミュータンス連鎖球菌の糖質代謝を阻害する、いわゆる無益回路を回します。
ミュータンス菌は、キシリトールを取り込むとリン酸化して、キシリトール5リン酸(x-5’P)にしま
す。しかしミュータンス菌は、それ以降の代謝系を持たないので、菌体内に(X-5’P)が蓄積して糖代
謝系酸素を阻害するのです。
⑤FAO/WHO(共同食品規格委員会)より、『1日の許容摂取量(ADI)を特定しない』という最も高い安
全性を与えられています。
味覚習慣からみたキシリトール
このようにキシリトールは、う蝕予防にとって好都合な素晴らしい甘味料といえます。しかし味覚
形成においては、その推奨法、予防に使用する場面を注意深く検討する余地がありそうです。砂糖
と同等の相対甘味度1の味覚をあえて乳歯列完成前の幼児に積極的に摂取させるのは、いかがなもの
でしょう。歯を傷めてしまう人とまったく同じ味覚習慣をつけてしまう恐れがあります。
たとえば、乳幼児のう蝕予防では、ミュータンス連鎖球菌が感染する19ヶ月から31ヶ月の間のいわ
ゆる“感染の窓”の時期に、乳幼児本人ではなく、母親など菌を伝播しやすい人を対象にキシリトー
ルを用いるとよいかもしれません。う蝕予防のためには、スクロースは食事時に摂取し、食間にキ
シリトールなど機能性食品を摂取するといった、メリハリのついた食習慣が重要です。
キシリトールの本質は酸を作らないこと、唾液の分泌を促すことで脱灰予防にはたらくことです。