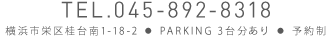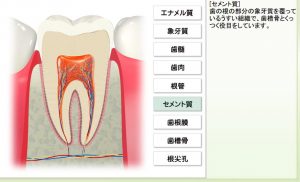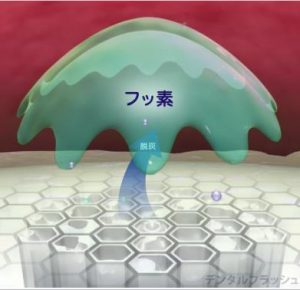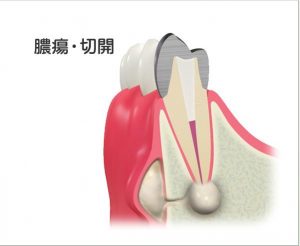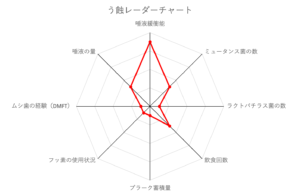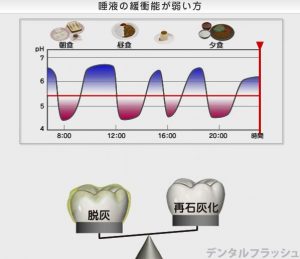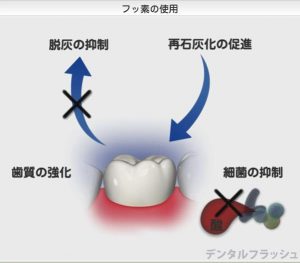人によってむし歯と歯周病の対策は違います。
ただ漠然とブラッシングを惰性でしていても、むし歯と歯周病は防げません。 一番良くないことは何となく惰性でのブラッシング。 各論は次回に譲るとして、今回はまずむし歯と歯周病の違いをもう一度 整理しましょう。1. 虫歯と歯周病はどう違うの?
歯のトラブルといえば「虫歯」と「歯周病」。
名前はよく聞きますが、実は原因も進み方も全く違います。
-
虫歯 …「歯」そのものが溶けて壊れる病気、歯に穴が開く病気
-
歯周病 …「歯を支える組織」が壊れる病気・初期は歯茎の腫れ、出血、末期は骨の溶解
つまり、虫歯は 歯の病気、歯周病は 歯を支える組織の病気 なのです。
2. 虫歯の特徴
-
原因:細菌が糖分を分解して酸を出し、歯が溶ける
-
症状:しみる、痛い、穴があく
-
進行:早ければ2か月で大きく悪化することも
-
治療:削って詰め物や被せ物をする、重度なら神経治療
👉 早期に見つければ「削らずに経過観察」で済むこともあります。
3. 歯周病の特徴
-
原因:歯ぐきにプラーク(細菌のかたまり)がたまり、炎症が起こる
-
症状:歯ぐきの腫れ・出血・口臭、進行すると歯がぐらつく
-
進行:ゆっくり進むが、気づいた時には重症になっていることが多い
-
治療:歯石除去、歯ぐきのクリーニング、重度の場合は外科治療
👉 初期の歯周病は「痛みがほとんどない」ため、気づかれにくいのが特徴です。
4. 虫歯と歯周病の共通点
実は全く違う病気でも、「予防方法」には共通点があります。
-
毎日の正しい歯みがき
-
フロスや歯間ブラシでのケア
-
定期的な歯科検診
幹なる部分は同じですが、人によって枝葉の部分が変わります。
5. まとめ
-
虫歯は歯が壊れる病気、歯周病は歯を支える組織が壊れる病気
-
虫歯は痛みで気づきやすいが、歯周病は気づきにくい
- むし歯はレベルによって削らなくても治せる方法があります。
-
共通する予防法は「毎日のセルフケア+歯科医院での定期検診」
👉 次回は「プラークと歯石の違い」について解説します。
歯みがきしているのにできる“歯石”って、いったい何者?